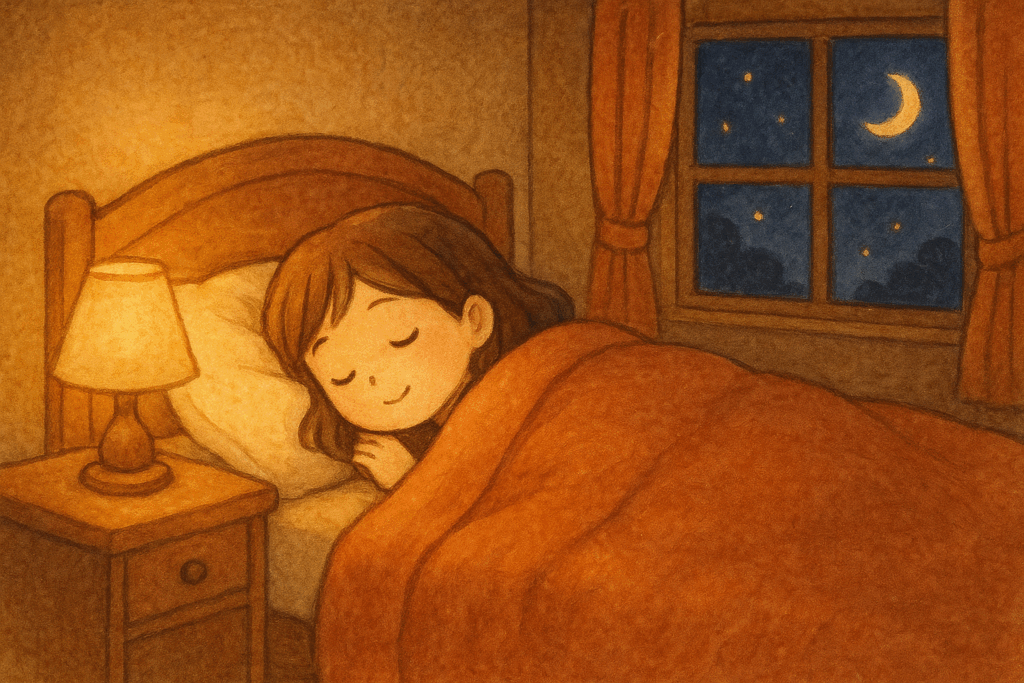2025年11月7日 立冬 なのですが、日中は、暖かく半袖の方もいらっしゃいました。が・・・
立冬(りっとう)— 冬の始まりを感じる日
秋の深まりとともに、木々の葉が赤や黄に染まり、空気が澄み渡る頃、日本の暦の上では「冬の始まり」を告げる日があります。それが「立冬(りっとう)」です。
この記事では、立冬の意味や由来、過ごし方、食べ物、ご紹介します。
日本の四季の移ろいを感じながら、心豊かな冬の始まりを迎えましょう。
◆ 立冬とは?
立冬とは、二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、毎年11月7日頃にあたります。2025年の立冬は【11月7日(金)】です。
「二十四節気」とは、太陽の動きを基準に1年を24等分した季節の指標で、古代中国で生まれ、日本でも農作業や暮らしの目安として使われてきました。
立冬は「冬の気配が感じられ始める日」とされ、暦の上でこの日から立春の前日までが冬になります。つまり、まだ体感的には秋のようでも、暦の上では冬の幕開けです。
◆ 立冬の頃の自然の変化
立冬の頃になると、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、空気が乾燥してきます。
山々の紅葉は見頃を迎え、街路樹のイチョウやモミジが風に舞う光景が美しい季節です。
また、澄み切った空に「冬の星座」が現れ始め、夜空が一段と輝いて見えるのもこの時期の特徴です。
空気の澄み具合:秋の終わりから冬の初めは湿度が下がり、空気中の塵が減るため、遠くの山や星がくっきりと見えます。
風の変化:北風が強まり始め、体感温度が下がります。冬支度を始める目安としても最適な時期です。
植物の様子:木々は葉を落とし、動物たちは冬眠の準備を始めます。自然界も冬モードへと切り替わる瞬間です。
◆ 暮らしの中の立冬
立冬は、古くから「冬支度を始める日」とされてきました。
衣替えや暖房器具の準備、こたつやストーブの点検などを行う時期でもあります。
● 冬の衣替え
セーターやコートなどの防寒具を取り出し、押し入れの中も衣替え。湿気が少ないこの時期に行うと、カビ対策にもなります。
● 食卓の冬支度
旬の食材を使った温かい料理が恋しくなる頃です。鍋料理やおでん、煮込み料理が食卓に並び始めます。
また、立冬に食べると良いとされる食べ物もいくつかあります。
◆ 立冬におすすめの食べ物
● 鍋料理
冬の定番といえば鍋料理。白菜や大根、ネギ、きのこ類など旬の野菜をふんだんに使うことで、体の中から温まります。特に「寄せ鍋」「ちゃんこ鍋」「味噌鍋」などは栄養バランスも良く、風邪予防にも最適です。
● 旬の魚
立冬の頃は、サンマやブリ、タラなど脂の乗った魚が美味しくなります。「寒ブリ」や「タラ鍋」はまさに冬の味覚の代表格です。
● 根菜類
大根、人参、ごぼうなどの根菜は、体を温める効果があるとされます。煮物や味噌汁に入れると、優しい甘みと滋養を感じられます。
◆ 心と体の冬支度
立冬は、自然だけでなく「心と体」も冬仕様に切り替える時期です。
冷えや乾燥を防ぐため、生活習慣を少し整えるだけで快適に過ごせます。
● 冷え対策
足元を温める靴下や湯たんぽを使い、体温を逃さないようにしましょう。
また、朝の白湯(さゆ)や生姜を使った飲み物もおすすめです。
● スキンケア
乾燥が進む季節なので、加湿器を活用し、保湿ケアを忘れずに。
ハンドクリームやリップクリームも欠かせません。
● メンタルケア
日照時間が短くなるため、気持ちが落ち込みやすくなることも。
朝の散歩や好きな香り(アロマ)を取り入れることで、心のリズムを整えましょう。
立冬は「ゆっくりと冬を迎える日」
立冬は、単なる季節の節目ではなく、「自然と調和しながら生きる知恵」が詰まった日です。
寒さを恐れるのではなく、「温かく暮らす工夫」を楽しむことが、冬の醍醐味といえるでしょう。
紅葉を愛でながら、温かいお茶を片手に季節の移り変わりを感じる。
そんな小さな瞬間に、豊かな時間が流れています。